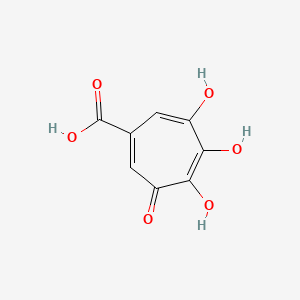階段から落ちた日の翌日くらいに、咳をしてもなかなか息が通らなくて強く咳き込んだら左の肋骨あたりに強い痛みを覚えた。あ、これ肋骨やったかな、と思いつつしばらく放っておいたが、階段から落ちたケツの打撲と肋骨の痛みでなかなかハードな日々だった。仕事をしながら、数時間おきに横になって休憩したり。深呼吸をして胸郭が広がったり、寝た姿勢になったりすると胸が痛む。座った姿勢でいると尻が痛む。眠りが浅い気がする。
そんな感じで痛みと闘いながら書いた原稿がようやく手離れしたので、整形外科へ。レントゲンでは明白な骨折はみられず。微小なヒビだと映らないので、そういうのがあるのかも、との診断で、鎮痛剤だけ出してもらった。
前にも咳で折れたことあったな、と思って検索したら、7年前の4月だった。このときははっきり骨が「く」の字に折れていたのを思い出した。
shioさんに教えてもらった「ななすけの散歩録」が面白くて、上がっている動画は全て見た。
短髪美人のななすけさんが散歩する番組。目力と👍とシャドウボクシングと犬が良い。街の歴史や暗渠の話をしてくれるので、ブラタモリ亡き後はこれを見れば良いのではないかと思った。三鷹の回で、なぜ太宰はあんな流れがちょろちょろの玉川上水で入水自殺できたのかという話を説明してくれていて、勉強になった。
飯(街食堂)と茶(喫茶店)と犬を大事にしているところが良い。フォーマットが決まっていて、ナレもアフレコのみで作っているのが落ち着いていて大変見やすい。声のことや、なぜこういう動画を作り始めたのかについては過去の番外編で一問一答している(1,2,3)。すぐに登録10万人超えるのではなかろうか。ただ、ファンと称する教え魔おじさんもたくさん寄ってきそう。寄ってきたら殴れ。鳩尾を。
動画作成は未経験だったというが、カメラの構図や編集のセンスがキレッキレで凄い。こういうふうに才能があって何かやりたい人は、一昔前ならテレビ業界やメディアに行ったのかなと思うが、今はもう自分でYouTubeでやって稼げるわけだし、そりゃあテレビがあれだけスカスカになるわけだな、と納得。
ご本人のtwitterも素晴らしい。下のLINE画像は見たことがあったが、ななすけさんだったとは。