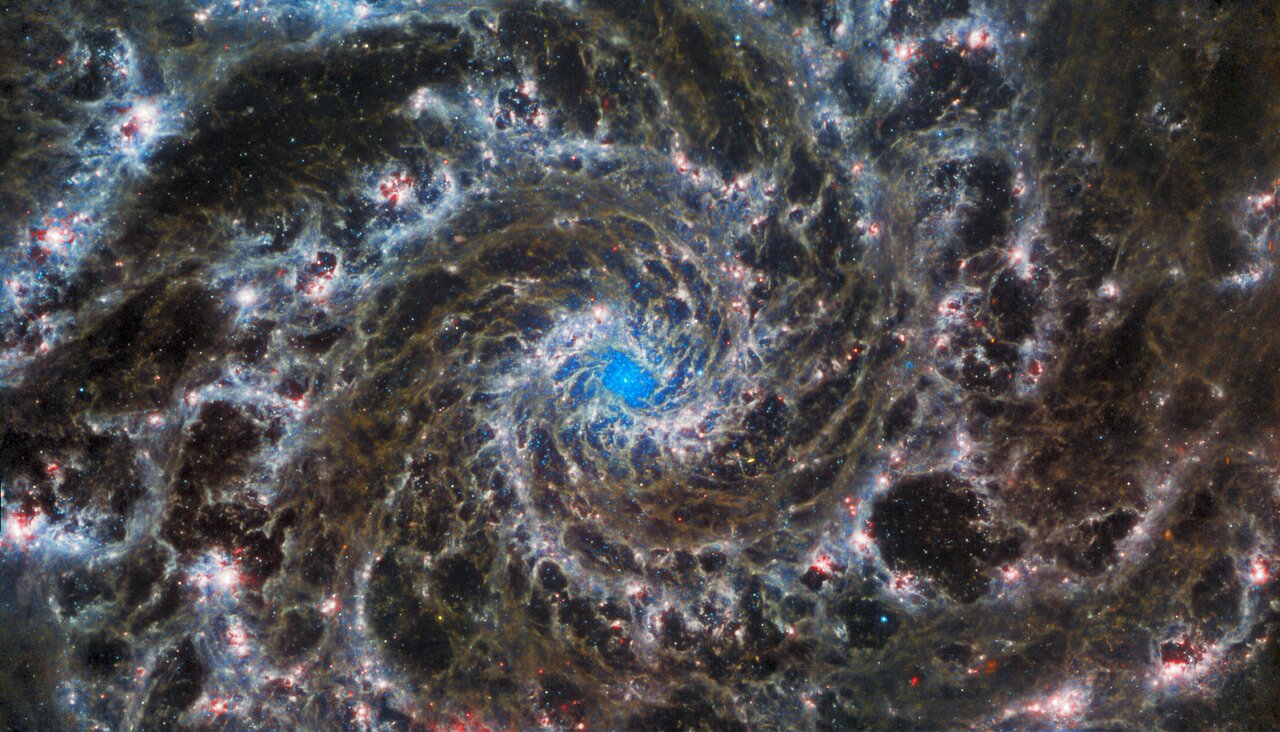@新宿ピカデリー。日曜朝4時開演のため、前夜に新宿のサウナにチェックイン。前に新宿でサウナ泊をしたのは、2013年のRIJFESに新宿からバスで参加したときらしい。PerfumeがRIJFESで大トリをとった年だ。もう10年前か。Perfumeまだやってますよ。凄いな。

前に泊まったサウナと同じような違うような、記憶が曖昧。今回はAKスパというところで、堅気でない人が結構利用することで有名らしい。実際、肌に絵が描かれている人を数人見かけた。刺青を入れている人にだって風呂に入る基本的人権はあるわけだから、刺青お断りという施設があるのはよく分からない。
仮眠室の設備は悪くないが、窓が開いていて外の騒音がずっと聞こえていたのと、寝ている人の中に歯ぎしりマンがいて、熱帯雨林の謎の鳥のようなギュイギュイという音がうるさくてあまり寝られず。耳栓をすると熟睡してしまって寝過ごしかねないので、あえて耳栓は使わなかった。
3時過ぎに新宿ピカデリー着。既に半分くらい埋まっていて、WT2ロンドン公演の映像が流れる中、座席で寝ている人が結構いた。開演までには全部埋まっていた。早朝なのに凄い。
公演はMC少なめで、客に通訳させるというのもなく、英語のMCを頑張ってやっていた。ただし、フレーズを丸暗記して喋っているので、イントネーションが違ったり、切っちゃダメなところで切ったりしてたまに通じてなかった。まあでも、大好きなPerfumeがなんか一生懸命英語で喋ってくれるから嬉しい! Yeah! みたいな優しい空気があった。
曲目はザ・ベストヒッツな感じ。最近外されがちな「ポリリズム」もやった。海外でやるときはこういうのがいい。やっぱりみんな一期一会の機会に有名曲を聴きたいわけだから。ただ、三人の体力がよくもったな。聴く方は盛り上がるけど、やる方は死人が出そうなセットリストだった。やばい。
新曲も披露された。可愛い系のすごくいい曲。早く正式に聴きたい。
2016年のCOSMIC EXPLORERツアーでやった「Perfumeの掟」を再演したのも含めて、PerfumeがPerfumeであることをいささかもやめておらず、体型も歌・ダンスも全く衰えを見せていないところに凄みを感じた。俺も頑張ろう。
久々に新宿に出たので、前日はサウナにチェックインする前にヨドバシで買い物。タワレコでも『PLASMA』のライブBDを購入した。新宿塔に上る9階までのエスカレーターを以前は歩いて上れたが、今やるとかなり息切れする。体力落ちてるな。