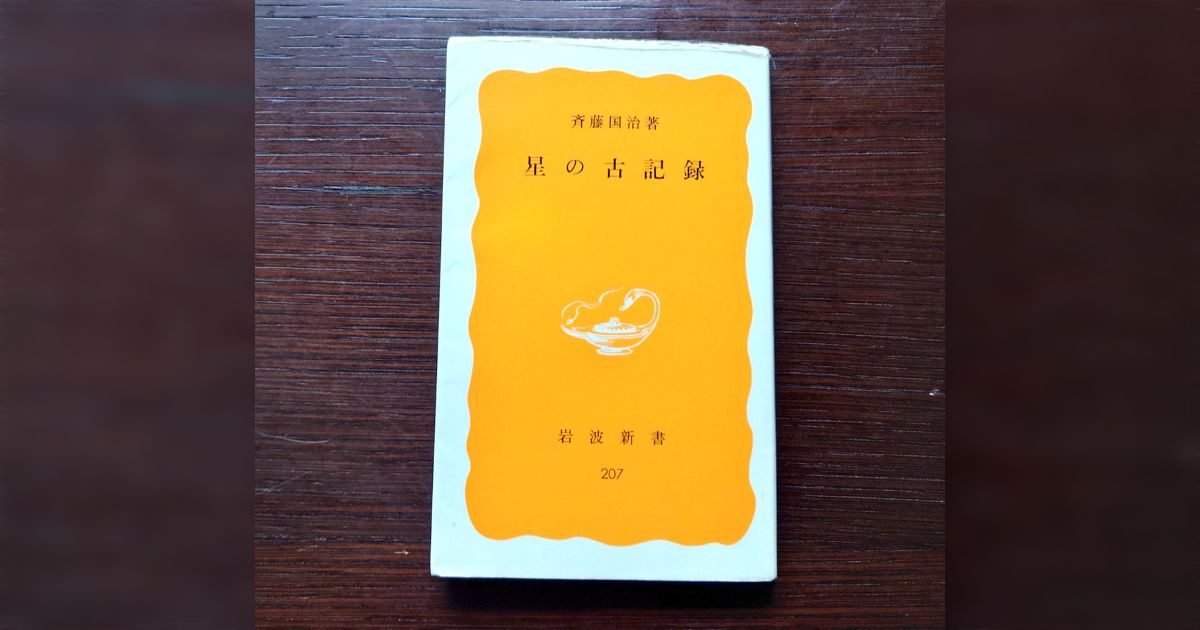斎藤国治著。古天文学の有名な本で自分も昔読んだ。twitter界隈で突然話題になったらしい。
最近は買えない状態だったが、twitterでの盛り上がりを見て岩波が即重版を決めたらしい。決断早。うちにも1冊あったはずだが見当たらない。売っちゃったか。
『星の古記録』で個人的に覚えているのは日食に関する記述。月の軌道面は地球の軌道面から5度くらい傾いているので、月は半月ごとに地球の軌道面(黄道)よりも上に来たり下に来たりする。2つの軌道面がちょうど交わる方向を月の「昇交点」「降交点」といい、月と太陽がこの付近にいる時期にしか日食は起こらない(月食も同)。月・太陽の視直径は0.5度なので、昇交点・降交点から離れたところで新月になっても、月と太陽は縦にずれていて重ならないわけです。月が昇交点・降交点に来るのは半月に一度だが、太陽は半年に一度しか来ないので、日食が起こる「食の季節」も半年ごととなる。
古代人も「食の季節」は知っていたが、食の季節に*自分の土地で*日食が起こるかどうかを計算する能力はまだなかった。よって、食の季節にはとりあえず日食が起こりますと予報しておいて、起こらなかった場合は「祈祷によって日食を防いだ」ことにした、と本書に書いてあった記憶がある。何という実際的な運用だ、と感動したのを覚えている。
月の昇交点・降交点は食を引き起こす重要な存在だったので、古代の天文学・占星術では太陽・月・5惑星(水金火木土)と並ぶ重要な「天体」とされた。中東や西洋では竜の頭としっぽ (Dragon’s head / Dragon’s tail) 、インドではラーフとケトゥと呼ばれた。この概念が中国・日本にも伝わり、この9天体をまとめて「九曜」と呼ぶようになった。細川家などの家紋になっている九曜紋はそういうわけで、太陽・月・5惑星・月の昇交点・月の降交点の9個を表している。